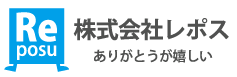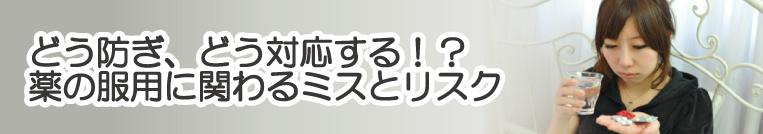
自ら薬を服用できない人に対し、看護師や家族などが投与を行う姿は一般的によくみられる光景です。しかし、そこには常に様々なミスの可能性が存在します。
ミスを防ぐにはどうすれば良いか?万が一ミスが起きた時にどのように対応するか?
考えてみましょう。
薬の服用前にミスを防ぐ
薬のミスで多いのが、「飲み忘れ」と「飲みすぎ」でしょう。毎食後に服用する薬剤を飲ませ忘れたまま時間が経ってしまった。逆に1日1度服用する薬剤を毎食後に飲ませていたなどです。申し送りのミスや記憶違いなどで、同じ薬を二重に服用させるケースも想定されます。
また、集団生活の中では薬の取り違えも起こり得ます。名前の似ている利用者の薬を誤って服用させる、薬の保管が甘く、利用者間で薬の入れ替わりが起きていた、などが考えられるでしょうか。
こういったミスを防ぐ手段としては、まず保管方法の改善が考えられます。
「利用者ごと」に「1回に服用する分の薬」を「服用タイミング」ごとに分けて保管する方法は基本といえるでしょう。透明ポケットつきのタペストリーや配薬ボックスなどで実践している施設も多いのではないでしょうか。
飲み忘れや飲みすぎの防止には、服薬確認表の使用が効果的でしょう。利用者の服薬を見届けた職員がチェックを入れることで、二重服用や服用忘れを防ぐのです。そして、こうした管理体制を複数の職員で確認していく事が重要です。薬の保管場所についても、高温多湿や直射日光の当たる場所は避け、冷暗所、薬によっては冷蔵庫など適温での保管を徹底しましょう。
ミスが起こった場合の対応
薬の服用後にミスに気付いたらどうするべきでしょうか。
まず、「利用者の状態(意識はあるか、苦しんでいないか、など)」を確認し、次に「どのような服用ミスだったか」を確認した上で、薬剤を処方した医師に連絡を取って指示を仰ぎます。誤服用の内容によっては即座の受診が必要なケースもあるため、状況を性格に医師に伝えて指示通りに動きましょう。利用者の意識がない、或いは意思があっても苦しがっている場合は、早急に救急車を要請しましょう。勿論、服薬ミスが起きたことを家族に連絡することも忘れてはなりません。
服薬ミスが起きた際は、職員自身が動揺してしまい冷静な判断が出来なくなる場合が想定されます。もしもの時に落ち着いて対応できるよう、日頃から事故時の対応マニュアル整備や事故を想定した訓練を行い、万が一の事態に備える事が必要です。事故が起こったとしても、的確な対応を行うことで被害を最小限に食い止めることは可能なのです。
より具体的な対応策を
ミスのリスクを減らす活動の手法を「リスクマネジメント」と呼びます。
リスクマネジメントで重要なことは、対応策を具体化すること。「服薬ミスを防ぎましょう」と呼びかけるのではなく、「服薬ミスを防ぐ為に○○と××の対応を行います」と具体的なシステムを作り上げるのです。
また、事故の際には個人の責任だけを追及することは避けるべきでしょう。個人の問題として事故を捉えると、事故の根本的な原因究明が疎かになるだけでなく職場そのものが責任追及を恐れて隠蔽体質になるリスクがあるためです。
どの様な注意・管理を行なっていても、人間の行動である以上ミスを100%避けることは出来ません。必要なのは、「出来る限りミスの可能性を減らすこと」と「ミス発生後の被害を出来る限り抑えること」です。
利用者・職員双方に過剰な負担の掛からないよう、現場の状況に合わせたミス防止の体制作りを考えていきましょう。