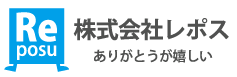世の中の雇用を促すシステムとして、労働者派遣事業や民間職業紹介事業については、労働力の需給調整を行う役割を担っているが、当然、一歩間違えると人身売買になりかねない。
そこで必ず許可が必要になってくるが、無許可、無届にも関わらず労働者派遣を行ったり、請負と称して、実際には労働者派遣を行う、いわゆる偽装請負など違法な事案が増えている。
労働者派遣事業の指導監督・行政処分は増えている!?
労働者派遣法等の法律に違反した場合、指導監督により改善させることになるが、特に悪質な場合は行政処分を行うこととなる。
具体的には、事業停止命令や許可の取り消し等といった重い対応を行うこととなる。
この指導監督件数は右肩上がりとなっており、また、24年度から25年度にかけては行政処分の件数が急激に増加しており、許可の取り消しを含む25件の行政処分となっている。
許可の取り消しの一例については、労働者派遣法違反について、何度も是正指導をされてきたのにも関わらず、複数の事業所で同様の違反が発覚し、2度目の指導中においても複数の事業所において法違反が認められたことから改善命令と共に事業停止命令を受けたそうだ。
しかし、事業停止期間中にも関わらず、派遣可能期間を超える労働者派遣を行っていたことや、大阪労働局職員が立ち入り検査をする際に検査を拒んだほか、妨害するなどの法違反があったっため派遣事業の許可が取り消された。
また、別のケースでは、熊本支店の事業内容を隠蔽することで、労働者派遣事業の許可基準を満たしているように見せかけて、不正に許可を取得していた。また、違法な労働者派遣を実施・継続していたことから許可を取り消したようだ。
需給調整指導官って!?
一般的な指導監督の際に、需給調整指導官といった人が苦情・相談や申告等の聞きとりや現場確認を含む事業調査を行うこととなっており、大阪労働局長から任命を受けることで「需給調整指導官」になることができる。
調査に際して違法行為が行われている可能性がある場合は原則としてアポイントなしで直接事業所に訪問し、派遣元や派遣先から事情聴取をするなどを行うとしている。
労働者派遣制度って?
許可・届出制と「登録型」「常用型」とあり、登録型派遣においては派遣労働を希望する労働者を登録し、相手方企業から求めがあった場合に、これに適合する労働者を派遣元労働者が雇い入れて相手方企業に派遣するというものだ。
また、常用型派遣は、派遣元事業主が労働者を常時雇用しておき、その事業活動の一環として、労働者を相手方企業に派遣するというものだ。
【「平成25年度 労働者派遣事業等の指導監督業務について」から一部抜粋。】